2週間ぶりの投稿になります。甘えていますね…。
試合に出れないとか、強い相手に勝てないとなっても本人の楽しいがどこにあるかでしか行動は変わらないとつくづく思うし、そうでないとならないと言うマインドになってしまうのもどうなのかと思っている。
低学年のうちはサッカーをすることが楽しい。
紅白戦で勝っても負けてもボールを追いかけ楽しかったとなる。
これがいつしか学年が上がりスタメンが決まり、対外試合で全く勝てない時も出てくる。
そこで自分の悔しいや勝つ楽しい気持ちから自分がどうなりたいのかを向き合っていく。
自分が何に楽しくなっていて、どうなると楽しくないのか。
その楽しいになるために自分はどうしたいのか、どうするのか。
以前にチームに入るかスクールのままにするかで悩んでいた選手が最終的にサッカーをやめた。
運動神経もよくそれなりに上達も早く、対外試合に出るのも良いかと思ったが本人は自分で周りの皆の様に練習したり、苦しいことをやってまでやりたいことではなかったと言いスクールは続け楽しく卒業していき中学ではサッカーを選ばなかった。
同じサッカーでも楽しいの感じ方が違う。チームによっても違う。
最初のチーム選びは保護者がやらないといけない。
そこからは本人と対話していくことがベストと思っている。
合わなかったら移籍も良いと思う。
人間としては「こうあるべき」と言う答えは存在しない。
しかし、チームや組織の中にいると組織が掲げる「べき論」に乗らないといけないことがある。
このべき論をどう捉えるかが本人のどうなりたいを抑制もするし飛躍すると思っている。
べき論ばかりに自分を合わせると無理が起こっていることもある。
親が言う「べき」やチームや学校が言う「べき」が基準となり生きづらくなる。
親も世の中はこうなっているから。
この世界で生きていくために必要だからと強いる。
しかし、一番見ないとならないのは本人の意思である。
そこに深い対話があるかどうか。
その「べき」はなぜ必要なのか、いつ必要なのか、などを対話してあげることが理想かなと思っている。
ボールを積極的に追いかけないといけないわけではないし、戦わないといけないわけではない。
それを選ぶのは自分である。
そこで監督に交代を告げられ、なんで交代したのだろう?と自分で考えればいい。
そうやって自分がどうなのかを感じていけば良いと思っている。
周りの仲間のプレイを見て感じ、相手のプレイを見て感じ、サッカーと言うスポーツで自分はどうなりたいのか。
そんな事を長い時間軸で見れば良いのかと思う。
〇年生までにこうなってないといけないわけではないような気がしている。
大事なのは本人がなりたい絵を描き、没頭する状態になるかどうか。
その為には行動しかない。
まずやってみる。やらせてみる。
そこで自分はどうなのかを自問自答させればよい。
その回数が多ければ多いほど思考の感性は豊かななのではないだろうか。
つまらない、楽しくないも一つの大事な行動からの経験である。
大人が経験した意味のなさそうなことも行動させないと感じれないのかもしれない。
どこまで先回りするのかが本当に親の役目なのか?
そんなことを考え直す夏休みでした(^^;
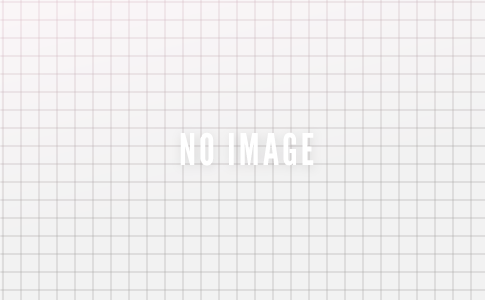

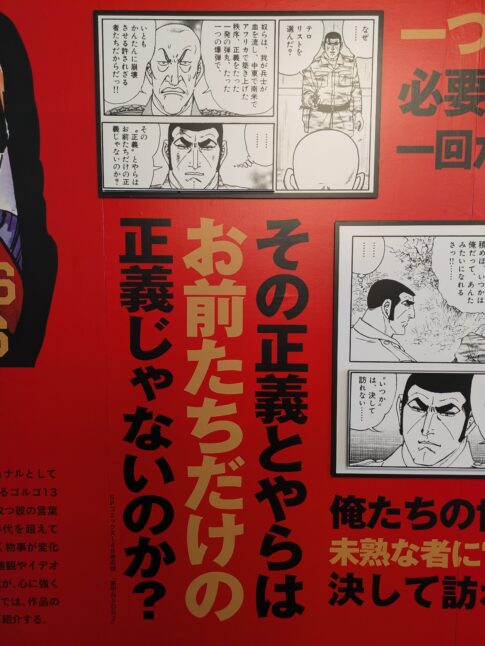

コメントを残す