どーもです。1週間空けてしまいました・・・。祝日によりずれていましたね。
今年は休みなくサッカー指導現場があり頭の切り替えが難しいのですが、昨年ライセンスをパワーアップし、クラブワールドカップの浦和レッズを見て、A代表のW杯予選生観戦を通して色々と感じさせられ常に右往左往しているさいたま市西区指扇でジュニアサッカーチーム烏天狗として活動している代表の岩田耕併です。
今の高校生を見ても、良い青年が多いと感じている。
毎度書いているが余計なことをしない子どもが増えている。
これは日本の教育機関や社会が目指した絵なのかもと思うと良いことも多々ある。
治安は良くなり、窃盗、万引きが減り、街もキレイである。
つまり、モラルやルールの際を攻める子どもが少なくなっている。
ルールの穴を見つけて破ろうとする子
屁理屈を言う子
がいない。
ルールを自分なりに解釈して曲げることは自分勝手とも取られて良くはない。
自分も自分の勝手な言い訳にしているところがあり嫌われている。
ルールが必要になった経緯は何なのか?
この背景を見ると本質が見えてくる。
サッカーにおいてはゲームである。
ルールを理解するとなぜオフサイドができたのかが知りたくなる。
オフサイドがないとどうなるのか。
その理由が分かるとオフサイドのギリギリを狙うようになる。
練習も今日はこんな制限やルールがありますよと提示する。
そんな制限の中でプレイして目的を達成するにはどうしたら良いのかと問いを投げかけている。
そもそも何を聞かれているのか分からない選手
また制限は分かったが目的を理解していないとルールを守っているだけで目的に向かっていない選手
などなどが多い。
つまり、世の中のルールも目的がある。ルールがないとこうなってしまうかも?と言うことからできたルールである。
そのルールの目的(なんの為にできたルールなのか)を普段から疑問に屁理屈で考えている選手はサッカーの呑み込みが早い。
ここを分からない選手は活躍するがもっと分かりやすい相手を一人抜いたとか、一人をマンツーマンでマークするとかはできるが複数のタスクが課されると困ってしまう。
サッカーは一つのことだけでは解決できない。
こと社会や人生においても複合している。
保護者も色々とできる、みえる人間になんてもらいたいはず。
となると、普段からの子供の行動がルールをまもることが目的になっていて、ルールの本質を追い求められていないのではないだろうか。
ルールができた背景には疑問にも思わず、だって先生が言ったからとか、コーチが言ったからとか言い訳して、誰彼構わず何度も同じ人にも挨拶しているチームみたいに脳が閉じた思考を放棄した状態になってしまう。
我が子がそんな人間でよいですか?
我々大人がどんなスタンスでいるかは子どもに直結に因果かっていると私は思っています。
ルールをどう捉えるか。
ルールをどう考えさせるか。

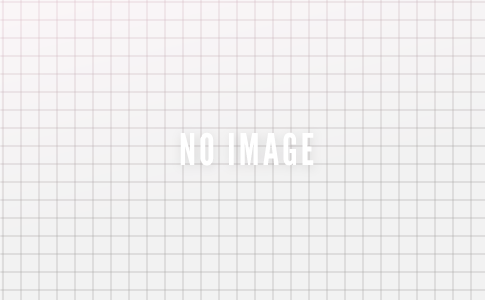
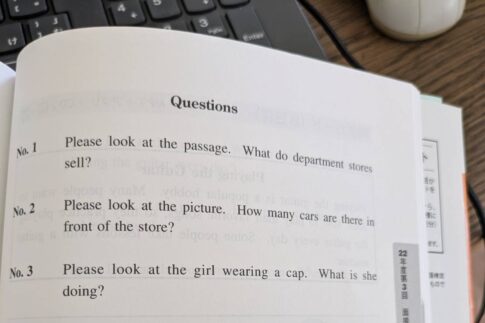




コメントを残す