こんにちは。更新1日遅れました・・・(^^;
週に1度電車を乗る機会があり社会に触れて、席を譲る青年が多くいることに世の中捨てたもんじゃないなと実感しているさいたま市西区差し扇で小学生対象のジュニアサッカーチーム烏天狗として活動している代表の岩田です。
以前にも書いているとは思いますが改めて先日感じたので記載したいと思いました。
ある選手は出来ること増えて成長してきているなと思って観ていたのですがグループでの練習の時に年上の選手達と組ましたらいつものように出来ませんでした。
それはそうだ。周りが自分より上手いと自負がある中でプレイすることは失敗する確率が高い自分は不安になり固くなる。大人でも誰もがそんな場面に遭遇したことはないだろうか。
緊張や固くなることは悪いことではない。むしろその状態を自分で知ることが大事で、そこからそんな自分だと発揮できていないことに向き合い、どう取り組むのかが次の段階である。
公式戦や代表や選抜などで行い勝った負けたや、自分の成功と失敗の振り返り方がとても重要だと思っている。勝ったから良しでもなく、負けたからダメってことでもない。成功の理由や失敗の理由を自分で分かっていくと次同自ような場面でトライの仕方が変わるはず。
ここで大事なのが「自分で」と言うこと。こちらの指導者や大人がアドバイスしたとて、言語化したとて彼らがその自分で「なんで上手くいったのか?なんでエラーしたのか?」に興味が無ければ全く頭に入っていない「はい!」と良い返事だけしている選手にしかならない。
自分でつかんだ選手は練習の仕方が変わる。自分でその出来ない自分を描いて出来る自分に変えようとして努力する。描けてない選手は目の前の練習を言われたこととしてこなすだけ。何も考えない。こなすだけ。
それで試合に出たいや、負けたら悔しいと言う。試合に出して負けて失敗して何も変わっていないけど?それなら勝てる相手の時しか出れない。上手くいかないようにしてくるのが対戦相手である。それを自分でなんとかしたいとなるマインドがないとそのままである。
よく「考えられる選手を」とどのチームも言っている。
このベースには自分で考えることが楽しいと言うマインドも大事である。
だから私が常々自分でやらせよう。
何で?と問いを投げかけて考えさせようと言っている。
判断が無い方がまとめやすい。
サッカーや人生は判断の連続、この判断が人間としてのサガなのではとも思う。
自転車の交通ルールがまた厳しくなる。危ないを自分で判断できなくしているようにも感じる。私は全てを否定している訳ではない。判断が難しい年代には基準があると判断しやすい。
しかし、判断できるようにするのが目的なのであれば基準だけで皆で判断を見守れるようにしたら良いと思っている。
信号を無くしたら逆に事故は減るかもしれない。運転する方も判断が求められるから。
イタリアの田舎町に毎年言って感じるのは信号限りなく少ない。自治で街を形成しているように思う。お年寄りや子供がいると見守っている。
より良くするとはルールを足して厳しくすることなのだろうか?
家庭の中でもルールについて話し合ってみたい。

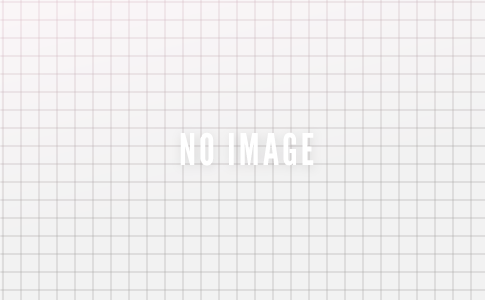



コメントを残す