日中の暑さに滅入っているがまだ6月なのかとビックリしている。
7月8月はどうなってしまうのか!!?
さて、私はクラブワールドカップが毎日行われていることに感謝している。
我が日本からも浦和レッズが参加している。
とても勉強になる。
相手にとって嫌だと思わせる怖いプレイをシンプルに選び続けてくる南米のチームにサッカーの大前提を問われている気がする。
サッカーは勝負
サッカーは戦い、闘い
真剣にそこに向かうから逞しくなり楽しくなる
やはり、この大前提がまだまだなのかと思い知らされた感じがしている。
浦和レッズは日本のトップレベル
それが簡単に負けてしまう。
結果以上に中身がかなりの差があるように思う。
技術のレベルでは大差がないとも見れるが、勝負の世界で力を発揮するところに関しては雲梯の差かなと。
海外に出て行った選手たちが皆んな同じことを言うと森保監督が言っていたが「同じサッカーだけど違うスポーツ」と。
Jリーグ開幕から歴史を刻み、文化としても発展してきたサッカーだが、ここでまた差を感じさせられたのではないだろうか。
ビルドアップ、ポゼッション、組織、前進、ドリブル、など色々なサッカーのワードをチームが用意してもそれを実走している選手たちが自ら負けたくない、勝負なんだと思いながらプレイすることが前提の上にあるということが抜けてしまう。
ボールをゴールにもっていく為にと考え抜いた結果が今日の相手にはビルドアップか、カウンターなのかと使い分けるのがサッカーで、その為の必要な技術を自分自身が欲するはずなのであるが、本人もどうしたら出れるとか、勝てるとか簡単に聞いてしまう。
勉強に近いことを感じたのが生きた知識と死んだ知識である。
算数を習って皆んな九九を覚える。
掛け算の式が出たら解ける。
しかし、文章問題で問われたら数字をどこに入れたら良いか分からない。
つまり、何を導くためのツールが計算式なのか分かっていない。
九九を覚えることが目的で使い方が分からないと言うのが起こっている。
定期テストなどの点数も大事だが、そこよりもその子がどこで躓いているのかを見ないとならない。
計算式の多い問題は得点高いのに、文章問題だと低いと言う現象は多々起きているのではないだろうか。この文章問題も式にできなかったり、単位を合わせられなかったり、など各々違う課題があると思っている。
点数を見て評価するのではなく何がわかっていないのかを測っていると思えばテストの点数は通過点に過ぎない。
むしろ躓きを解消したら突然使い方が分かって結果は飛躍するかもしれない。
サッカーも同じように手段を詰め込むことで本質からずれる可能性が高いし、それを繋げることを指導者が教えるだけだと永遠に平行線のままで自分の生きた知識になっていない。
手段を繋げることも大人が必死に教えてしまうから自身でつかんでいない。
やはり大前提が自分が負けたくないから考えると言うものを持ち合わせることが非常に大事なのかと思っている。
学校教育を否定しているのではなく、子どもに常に疑問を持たせ、受け身の状態にさせないことが大人の役目なのではないだろうか。
授業の在り方、この教科に興味を持って「なんで?」自身が思うことが前提なのではないだろうか。
主体性と言いながらルールが多く動かないほうが怒られないでむしろ良い子だねと褒められたりしちゃうから大人しく主体性がない子どもが増えているのではないだろうか。
主体性は求めることではなくて小さいころ皆んな持っていたものである。
それを削ぎ落しているのは我々大人側かもしれない。
もっとほっといて自分自身で良い悪いや安全危険などを実体験として持たせることから始めたい。
今差し伸べている手は、声がけは本当に子どものためになっていますか?

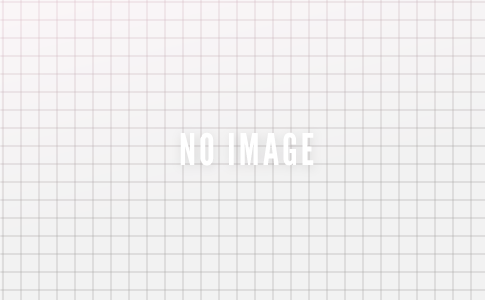



コメントを残す