どーもです。オクラって英語だったのを最近知って、言われてみるとカタカナだなと思い調べるとエリンギなども日本語からでなはなく、知らないことまだまだ沢山あるなーと思い学びの毎日に活力を見出しているさいたま市西区指扇でジュニアサッカーチーム烏天狗として活動している代表の岩田耕併です。
元麹町中学校校長の工藤勇一先生が言う日本の良さでもある心の話しがまさにと感じたことがあります。
日本人は心が行動に出ると言い良いこともある。
気を遣う文化で相手がどう思うかを考えて行動をとる。
物を持ってあげるのに「おせっかいかな」と心で思ってしまうと動けない時がある。
席を譲るのもそう。高齢と言っているみたいで嫌がるかなとか思うこともある。
またはゴミなど拾ったりすると偽善者だとか、先生に評価されたいから、人が見てるから良いことをしてるなど勝手に行動の背景を作っている。
しかし、良いことをしていると言う事実はどんな思いだろうが変わらず良いことなのだから良いはずである。
ここが中々動けない日本人文化を形成しているのかもしれないと自分も思う。
自分も大勢の中にいると社洒落ない。
ファーストペンギンになれない。
周りを気にする。これは悪いことではない。
しかし、ことサッカーにおいてはチームで目的を達成するのに受け身でいる選手がいることは時にそれでも良いが受け身でいると言うことは後手になるので苦しくなる。
自分から行動をとれるようになるとチームは活気があふれる。
その行動ができないのは
間違いだったらどうしよう
失敗したら皆に迷惑かける
など頭によぎるからかと思う
このマインドを否定しているのではなく
このマインドをどう打破していくのかを考えようと言っている。
自信を持つ
自己肯定感
などが言葉で言われること
これを積み上げるには自分で意識して、周りからどう思われようが自分が良いと思ったことを率先して動くことが大事なのかと思っている。
行動が心を変える。
あの人を嫌いでも挨拶するし
誰かが見てなくてもゴミ拾ったり、片づけたり
小さいことでも動くことにより動くことが当たり前になっていけば
サッカーにおいても自分で考え良いことに対して動くことができるのかもともと考える。
親が、先生が、コーチが、言うからやる。
それがスタートでも、やらされるが嫌でも
自分から何かに動くことが心を形成し心を強くしていくのかもと改めて思わされた。
我々大人もそんな背中を子ども達に見せて感じさせれるように行動をとりたい。
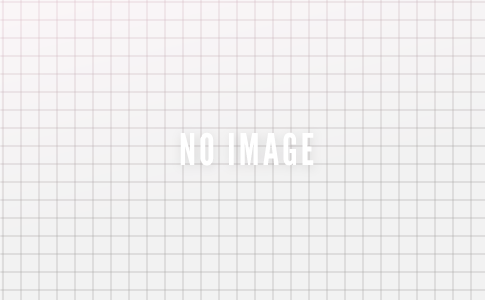



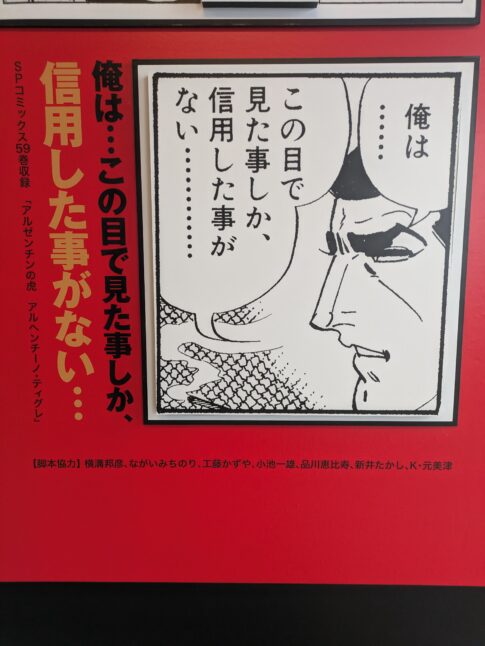
コメントを残す