こんにちは。都内の人の多さに改めて驚かされ、こんだけの人が本当に何か目的もってここに集まっているのか?と疑いたくなる性格のさいたま市西区指扇地域でジュニアサッカーチーム烏天狗JrFCを代表している岩田耕併です。
さて、サッカーにおける主体性について例題を出して考えたい。
チームでテーブルを早く綺麗にしてくださいと言うゲームがあったとします。
コップやお皿が出ているのに布巾でふきだすのは効率が悪い。
では先にコップなどを片付けから始めて何も無くなってから拭くと拭きやすい。
しかし、コップが1個しか出ていなかったら、片手で持って拭くのも早い。
コップを片付けてからやると良いと習うとコップの片付けが目的になって、必ずコップを片付けると言う作業になる。なぜコップを片付けると効率が上がるのかは分かっていない子はコップの片付けの質を磨く。
これを悪いとは言っていない。かなりの量を持てるようになるなど特質したことによる活躍もある。その質を上げることも必要である。
しかし、そもそもの目的はなんだ?
早く綺麗にすること。ここに向かっているのかどうかを問い続けることが前提である。
サッカーで良い選手の例では、より早くするにはどうなのか?
この問いを自問自答していくことを楽しみながら行なっている選手が出来ることが増えている。気付きが早く成長していくので試合に出しても考えて行動を取ろうとする。
もちろんこちらが考えていると思っていても実は出来ちゃっていたと言うこともある。
しかし、目的からズレている選手はちょっと難しい問題、相手になったときに動けないし、動いていることが役にたっていないことがある。
もちろん全く考えていないとは言わないが、そのような選手には簡単な状況から何をしたら良いのかの整理をしていくことが大事かなと思っている。
何が分からないのかをひもといていく。
これも全て自分で考えようとすると言うのが前提にある。
これを持ち合わせていない子が多々いる。
言われたことをやる。言われたことが正解。
こちらのアプローチもそうだが関係性が上下関係の時は最悪になる。
上が怖いから下は言うことを聞く。
大人に力で勝てない子供は言うことを聞かせやすい。
静かにしていたり余計なことしない子供は世間の良い子ではなく考えていないロボット化した子になっている可能性がある。
子供が考えて動かないといけない環境をいかに用意できるか。
またその環境にチャレンジし続けられる空気があるか。
これが選手を大きくしていく作業だと思っている。
そして、出来ないからってその人を否定しているわけでない。
大人が他と比べて出来ないことにしか目がいかないと子供も結果にしか目が行かず、それを逃れるのは他人のせいにする。
我々は自分がどうなのかを問うことを楽しめるような心であることを大事にしたいと思っている。
主語を「自分は、私は、僕は」意識して行動をとらせたい。




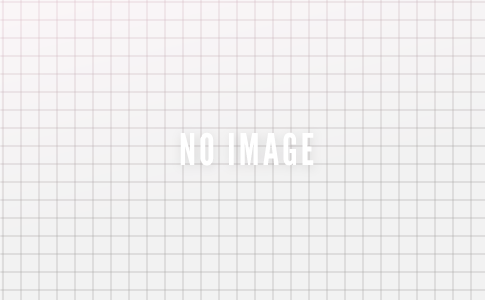


コメントを残す